Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/techme/techmebrains.co.jp/public_html/wp-content/themes/techme-brains-child/single.php on line 45
Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/techme/techmebrains.co.jp/public_html/wp-content/themes/techme-brains-child/single.php on line 45
目次
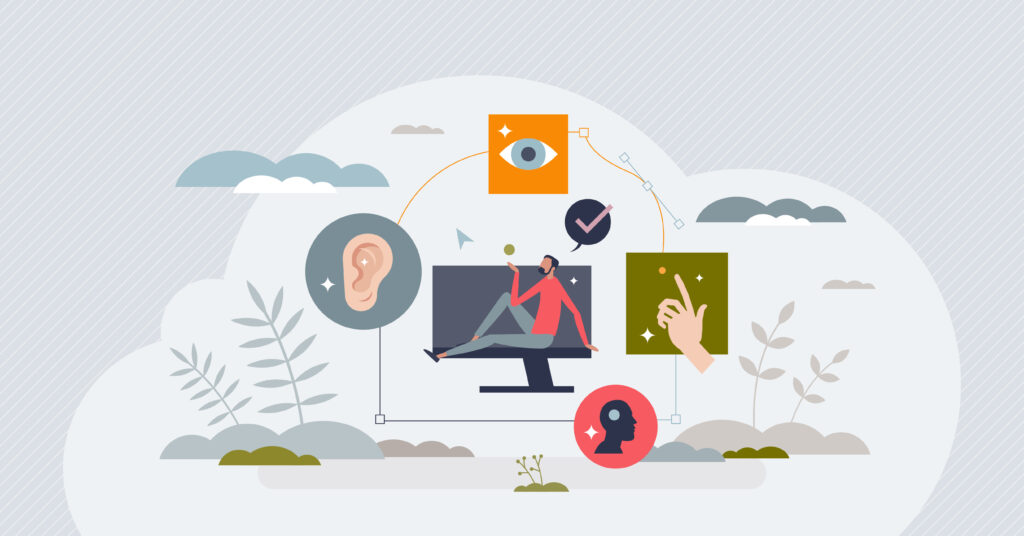
2024年4月に施行された改正障害者差別解消法により、今まで努力義務であった民間事業者の「合理的配慮の提供」が義務化されました。
この法改正を受け、「自社サイトのウェブアクセシビリティはどこまで対応すれば良いのか」と戸惑う担当者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、ウェブアクセシビリティの法的背景や、改正障害者差別解消法における「合理的配慮」の解釈を分かりやすく解説します。
法律遵守のための手順と対応を怠るリスク、企業が得るメリットなど、今後の対策に役立つ情報をまとめているので、ぜひ参考にしてください。
ウェブアクセシビリティを規定する日本の主要な法律・規格
ウェブアクセシビリティへの対応は、企業の社会的責任やユーザビリティ向上のためだけでなく、複数の日本の法律や公的な規格に基づいて行われています。
特に、2024年の法改正を経て、ウェブサイト対応の重要性はかつてないほど高まっています。
ここでは、ウェブアクセシビリティ対応の根拠となる最も重要な法律と規格について見ていきましょう。
障害者差別解消法(障がい者差別解消法)
この法律は、障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、行政機関や民間事業者に対して「合理的配慮の提供」を求めることで、障がいのある人もない人も共に生きる共生社会の実現を目指すものです。
2024年4月の改正施行により、これまで行政機関や自治体に対してのみ義務付けられていた「合理的配慮の提供」が、民間事業者にも法的に義務化されました。
この「合理的配慮」には、情報提供手段としてのウェブサイトやアプリにおける配慮も含まれます。
つまり、ウェブサイトにバリアがある場合、それは法的義務違反のリスクにつながる可能性があるということです。
参考:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律|e-Gov 法令検索
JIS X 8341-3(日本工業規格)
「JIS X 8341-3」は、直接的な法律ではありませんが、日本の公的な機関や企業がウェブアクセシビリティ対応を進める上での技術的な指針となる日本工業規格です。
ウェブコンテンツのアクセシビリティを確保するための具体的な要件を定めており、国の行政機関や地方公共団体がアクセシビリティ目標を達成するために参照すべき根拠となっています。
国際的なウェブアクセシビリティの基準である「WCAG 2.1」とも高い互換性を持っており、日本のウェブアクセシビリティ対応が世界標準に沿っていることの裏付けともなっています。
企業が具体的な対応を行う際、このJISが定める基準を参考にすることが最も確実です。
参考:JIS X 8341-3:2016 解説|ウェブアクセシビリティ基盤委員会(WAIC)
その他の関連法規
ウェブアクセシビリティに直接的に関わる法律は他にもあります。
その一つが「バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)」です。
公共交通機関や建築物など、主に物理的な移動のバリアフリー化を促進するものとして知られていますが、実はその目的には「情報提供のバリアフリー化」も含まれています。
また、自治体によっては、国の法律に加え、独自の情報バリアフリー条例などを定めている場合もあります。
ウェブアクセシビリティ対応に取り組むことは、法的なコンプライアンスを強化するだけでなく、すべての人に対する情報保障という企業の社会的責任を果たすことにつながります。
参考:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律|e-Gov 法令検索
改正障害者差別解消法における「合理的配慮」とウェブサイト
2024年4月の改正障害者差別解消法の施行は、企業のウェブサイト運営に大きな変化をもたらしました。
義務化された「合理的配慮の提供」が、ウェブサイトにおいて何を意味するのかを正しく理解しておく必要があります。
「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮」
改正法が禁止する「不当な差別的取扱い」とは、正当な理由なく、障がいを理由としてサービスや情報の提供を拒否したり制限したりすることです。
ウェブサイトにおいては、サイトの仕様によって障がい者が情報にアクセスできない状態がこれに当たります(例:視覚障がい者が利用できない予約フォームしかない、など)。
一方で「合理的配慮」とは、そうした情報アクセス上の障壁を取り除くため、個別の状況に応じて過度な負担にならない範囲で改善・調整を行うことです(例:視覚障がい者のために画像に代替テキストを適切に付与する、など)。
ウェブサイトに潜む「不当な差別」を取り除くことが、民間企業にも求められています。
ウェブサイトにおける「合理的配慮」の具体例
ウェブサイトにおける「合理的配慮」は、具体的なウェブアクセシビリティの対応項目と深く結びついています。
例えば、視覚障がいを持つ方のために、スクリーンリーダー(画面読み上げソフト)が内容を正しく伝えられるよう、画像に代替テキスト(alt属性)を設定することが挙げられます。
また、マウス操作が難しい方のためにキーボード操作の完全対応を確保することも一例です。
聴覚障がいを持つ方へは、動画コンテンツに字幕や文字起こし(トランスクリプト)を提供することが合理的配慮に当たります。
さらに、認知・発達障がいを持つ方へは、専門用語を避けたり、簡潔な文章構造にしたりすることも配慮の一つです。
「過度な負担」の判断基準
「合理的配慮」は義務化されましたが、その対応が事業者にとって非現実的なほど重い負担となる場合は、提供しなくても良いとされています。
これが「過度な負担」という概念です。
ただし、この判断は事業者側が一方的に行うものではなく、事業規模や財政・人員の状況、対応にかかる費用対効果、その措置の実施によって得られる利益や影響など、多角的な要素から公正に評価されます。
つまり、単に「面倒だから」という理由では認められないのです。
中小企業や個人事業主であっても、可能な範囲で対応することが求められており、特にウェブサイトという重要な情報提供手段においては、無視できない対応となっています。
法的義務化に対応するための3つのステップ
改正障害者差別解消法への対応は、多くの場合、ウェブ担当者が主導して計画的に進める必要があります。
ここでは、「合理的配慮」の提供義務を果たすため、具体的にどのような手順を踏んでいけば良いのか、実務的な対応を3つのステップに分けて解説します。
①目標とする適合レベル(WCAG/JIS)を定める
最初に行うべきことは、「どこまで達成するか」という具体的なゴールを設定することです。
法的義務化に対応するための最低限の品質基準として、国際的なガイドラインである「 WCAG 2.1(Web Content Accessibility Guidelines)」のレベルAA、あるいはそれと互換性のある「JIS X 8341-3」のレベルAAを目標とするのが一般的です。
目標を明確にすることで、改修の範囲と必要な予算が定まります。
この際、経営層や法務部門とも事前に合意を形成し、「このレベルを達成することで、企業の法的な要求を満たす」という共通認識を持つことが重要です。
②現状のウェブサイトのアクセシビリティを診断・把握する
次に、決めた目標レベルに対して、今の自社サイトがどの程度対応できているのかを客観的に確認しましょう。
これは、対応すべき具体的な問題点を正確に洗い出すために必須です。
ウェブサイト全体にわたる問題点を網羅的に洗い出すためには、専門の検証ツール(自動診断)を活用して技術的なエラーを特定しつつ、専門家による手動診断も併用することが推奨されます。
特に、ツールだけでは判断が難しい「キーボード操作のしやすさ」や「文脈の理解しやすさ」といった部分は、専門家の視点が必要です。
「Accessdove」では、サイトのアクセシビリティの状態を無料でチェックできます。
サイトのURLを入力するだけで登録も不要ですので、ぜひ以下のページからお試しください。
③改修計画を策定し、継続的な運用体制を構築する
診断によって洗い出された問題点に基づき、具体的な改修計画を策定します。
すべての問題を一度に解決するのは難しいため、影響度の高い問題(例:予約フォームが操作できないなど、機会損失に直結するもの)から優先順位をつけて改修を進めることが重要です。
また、ウェブサイトのアクセシビリティ対応は一度の改修で終わりではなく、コンテンツの追加・更新の度に品質を維持しなければなりません。
法律遵守を維持し続けるためには、サイト制作に関わる社員全員を対象とした教育や、アクセシビリティガイドラインの策定といった継続的な運用体制を構築する必要があります。
ウェブアクセシビリティの法対応を怠るリスク
改正障害者差別解消法の施行により、ウェブアクセシビリティへの対応を怠ることは、法的・経済的・社会的なリスクを負うことを意味します。
ここでは、ウェブサイトのアクセシビリティ対応を後回しにした場合に、企業が直面するリスクについて解説します。
行政指導・勧告を受ける法的リスクを負う
改正障害者差別解消法に基づき、ウェブサイトが原因で障がい者に情報アクセス上の「合理的配慮の不提供」があると判断された場合、企業は行政指導や勧告の対象となる可能性があります。
この法律では、差別解消に向けた取り組みを要請し、指導・勧告に従わない場合には公表される可能性も示唆されています。
行政から指摘を受ければ、技術的な問題では済まず、コンプライアンス上の重大な問題として扱われるのです。
企業ブランドと信用の失墜を招く
ウェブサイトのバリアが原因でユーザーが情報にアクセスできない状態が続くと、障がい者や高齢者、さらにはそのご家族といった幅広いステークホルダーからの信頼を損なうことにつながります。
特に、現代社会では企業の倫理的・社会的な責任(CSR)が厳しく問われるため、「特定の層を排除している」というイメージは、企業イメージやブランド価値を深刻に毀損しかねません。
一度失った信頼を回復するには、多大な時間とコストがかかります。
ウェブサイトは企業の顔であり、その顔にバリアがあることは、社会的な信用失墜に直結するリスクとなります。
巨大な潜在顧客層へのアクセス機会を損失する
ウェブアクセシビリティに対応していないサイトは、ウェブサイトを利用できないユーザーを恒久的に排除していることになります。
「利用できないユーザー」には、障がい者や高齢者だけでなく、一時的に手が使えない人や、低速な回線を利用している人なども含まれます。
この層は、決して無視できない潜在顧客層です。
対応を怠ることは、こうした顧客層からの売上や取引の可能性を、企業自らが失っていることを意味します。
競合他社が対応を進める中で、自社だけがアクセシビリティのバリアを残すことは、経済的なリスクとなるのです。
ウェブアクセシビリティの法対応を進める企業メリット
ウェブアクセシビリティへの対応は、改正障害者差別解消法への「義務的な対応」という側面だけではありません。
むしろ、これを契機として対応を進めることは、企業にとってビジネスの成長とウェブサイトの品質向上というメリットをもたらします。
ここでは、代表的な3つのメリットを見ていきましょう。
新たな顧客層の獲得と市場の拡大を実現する
アクセシビリティ対応は、これまでウェブサイトの情報バリアによって排除されてきた層を、新たな顧客として取り込む機会を生み出します。
日本の高齢者や障がいを持つ人々は、決して小さな市場ではありません。
こうした層が、ストレスなく自社の商品情報を見たり、サービスを利用したりできるようになることで、潜在顧客が顕在化し、市場の拡大に直結します。
競合他社に先駆けてウェブアクセシビリティ対応に取り組むことで、市場における優位性を確立できるでしょう。
誰一人取りこぼさない姿勢が、結果として企業の売上を支えることにつながるのです。
ウェブサイトのユーザビリティとSEO効果を向上させる
アクセシビリティ向上のために行う施策の多くは、すべてのユーザーの使いやすさ(ユーザビリティ)と、検索エンジンの評価(SEO)を高めることにつながります。
例えば、見出し構造を正しく整備したり、画像に適切な代替テキストを設定したりといった施策は、視覚障がい者だけでなく、Googleなどの検索エンジンのクローラーにもコンテンツの構造と意味を正確に伝えるのです。
その結果、検索順位の向上という間接的なSEO効果が期待できます。
また、分かりやすいナビゲーションやシンプルなデザインは、障がいや年齢に関わらず、全ユーザーの満足度(UX)を高める効果があります。
長期的な事業継続性とリスクヘッジを確保する
法規制や社会的な要請は、今後さらに厳しく高まっていくことが予想されます。
このような動向を見越して早期にアクセシビリティ対応を完了させておくことは、長期的な事業継続性と優れたリスクヘッジにつながります。
法令が強化されてから慌てて大規模な改修を行う場合、時間もコストも膨大にかかってしまうでしょう。
しかし、今のうちに計画的に対応を進めておけば、将来的な大規模な手戻りや、法的な紛争リスクを未然に回避できます。
アクセシビリティは一過性の流行ではなく、企業のウェブサイトが備えるべき永続的な品質基準として捉えることが、経営戦略上も賢明な判断といえるでしょう。
まとめ
2024年4月の改正障害者差別解消法の施行により、ウェブアクセシビリティへの対応は、もはや法律違反を避けるための最低限の対策ではありません。
現代の企業ウェブサイトにとって欠かせない基本的な品質基準であり、社会的責任を果たすとともに、ビジネスチャンスの拡大に直接つながります。
アクセシビリティ対応は、品質向上・SEO効果・新たな顧客獲得というメリットをもたらすのです。
しかし、法対応と品質向上を効率的に進めるには、人力での改修やチェックには限界があります。
継続的な品質維持を実現するためには、専門のアクセシビリティ検証ツールの活用が不可欠です。
法対応と高品質なウェブサイト運用を両立させたいとお考えの方は、タグ一行で導入できる「Accessdove」をチェックしてみてください。


