- ウェブサイトの「文字サイズ変更機能」はなぜ必要?アクセシビリティ対応のポイントとメリットを解説!
- ウェブサイトの「音声読み上げ機能」とは?利用者から見たメリットと導入時の注意点を解説!
- 情報バリアフリーとは?ウェブサイトにおける重要性と実現のためのポイントを解説!
- 2024年4月施行「障害者差別解消法」改正とウェブ対応の義務化|企業が今すべきこととは?
- ウェブアクセシビリティ対応はなぜ必要?導入のメリットから義務化の動向まで徹底解説!
- ウェブアクセシビリティとは何か?初心者向けにわかりやすく解説
- ウェブアクセシビリティの義務化はいつから?罰則はあるの?
- ウェブアクセシビリティのJIS規格について徹底解説!
- ウェブアクセシビリティの「A」「AA」達成基準を詳しく解説!
- ウェブアクセシビリティのデメリット4つとその解決策
目次
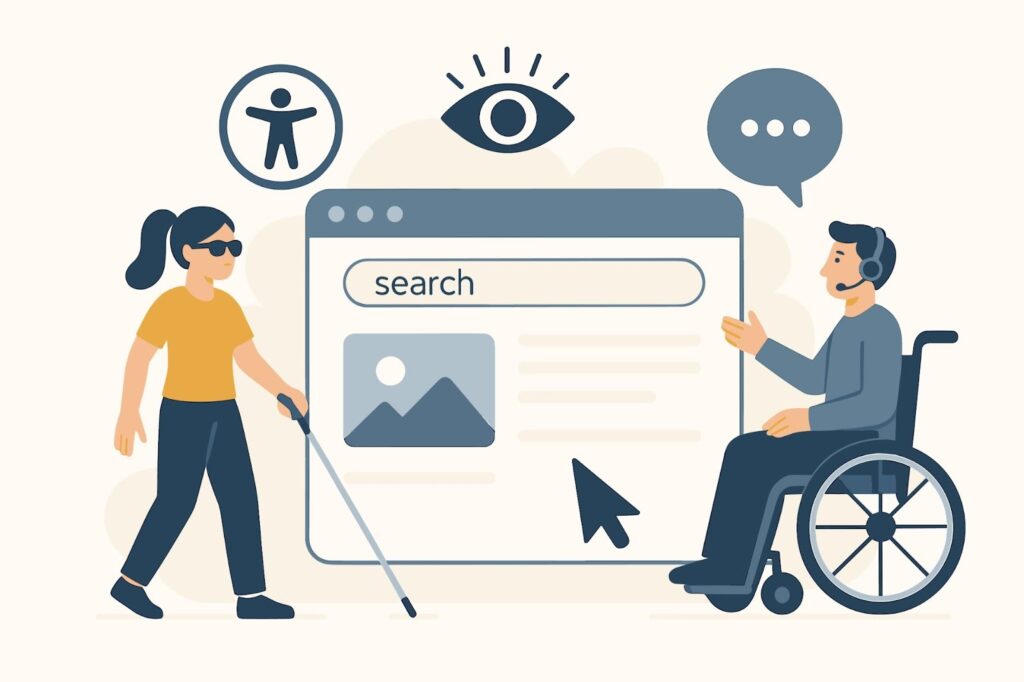
ウェブサイトを運営する上で、「誰もが使いやすいサイト」にすることは、今や欠かせない課題です。
特に高齢化が進む日本では、視力の低下や身体的な理由から、ウェブサイトの文字を読むのが難しいと感じる方も増えています。
「音声読み上げ機能」は、そうした方々がウェブサイトの情報をスムーズに利用できるようにするだけでなく、移動中や作業中の「ながら聴き」ニーズにも応え、より多くのユーザーにサイトを届けるための有効な手段です。
この記事では、ウェブサイトに音声読み上げ機能を導入する必要性から、その具体的なメリット、そして導入時に注意すべきポイントまで分かりやすく解説します。
ウェブサイトにおける「音声読み上げ機能」とは?
ウェブサイトの情報は、目で読むのが一般的です。
しかし、視力が低い方や一時的に文字を読むことが難しい方にとって、文字だけのコンテンツは大きな障壁となります。
そうした方々がウェブサイトをスムーズに利用できるようにするための技術が「音声読み上げ機能」です。
ここでは、その機能の概要と、主な種類について解説します。
「音声読み上げ機能」の概要
音声読み上げ機能とは、ウェブサイトに表示されているテキスト情報を、合成音声に変換して読み上げる技術です。
目から文字情報を得るのが難しいユーザーでも、耳からコンテンツの内容を理解できるようになります。
音声読み上げ機能は、視覚に障がいがある方だけでなく、老眼などで文字が読みにくくなった高齢者の方、また文字の認識が困難な学習障がいのある方など、多様な人々をサポートします。
さらに、音声読み上げはウェブサイトを「聞くコンテンツ」に変えるため、料理や移動中など、画面を直接見られない状況での「ながら聴き」ニーズにも応えられます。
ウェブサイトの情報を音声で聞けるようにすることで、これまでアクセスできなかったユーザー層にサイトを開放し、使いやすさを飛躍的に向上させることにつながるのです。
「音声読み上げ機能」の種類
ウェブサイトの音声読み上げ機能には、大きく分けて2つの種類があります。
ひとつは、「ブラウザ標準搭載機能」です。
特定のウェブサイトに限定されず、パソコンやスマートフォンに最初から備わっている機能やソフトウェアのことを指します。
代表的なものが「スクリーンリーダー」で、視覚障がいのある方がPCやスマホを操作するために利用します。
ウェブサイトが正しく作られていればコンテンツを正確に読み上げてくれますが、ウェブサイトの構造に問題があると、正しく読み上げられなかったり読み飛ばされてしまったりすることがあります。
もうひとつは、「ウェブサイト独自に実装する機能」です。
特定のウェブサイトに読み上げ機能を埋め込むもので、「ウェブサイト読み上げツール」と呼ばれることもあります。
ユーザーはボタンひとつで読み上げを開始でき、利用したいページだけを簡単に聞けるようにするメリットがあります。
ウェブサイト側で読み上げを最適化できるため、複雑な情報でも正確に伝えることが可能です。
音声読み上げ機能がもたらすメリット(利用者側・企業側)
音声読み上げ機能は、ウェブサイトに欠かせない機能になりつつあります。
ウェブサイトを利用する人だけでなく、それを運営する企業にとっても大きなメリットがあるのです。
ここでは、その具体的なメリットを、利用者側と企業側の両面から見ていきましょう。
利用者側の2つのメリット
音声読み上げ機能がもたらす最大のメリットは、「情報が取得しやすくなる」ことと「マルチタスクが可能になる」ことです。
まず、「情報が取得しやすくなる」という点ですが、これは主に視覚に障がいのある方や、文字を読むのが苦手な方に恩恵をもたらします。
どんなに優れたウェブサイトでも、文字が読めなければ情報にたどり着くことができません。
音声読み上げ機能があれば、耳からコンテンツの内容を理解できるため、読書が困難な状況でも必要な情報をスムーズに得られます。
また、長文を読む際の目の疲れを軽減する効果も期待できます。
次に、「マルチタスクが可能になる」という点です。
これは、特定の障がいを持つ方だけでなく、すべての人にとってのメリットとなり得ます。
例えば、通勤中の電車内・料理中・運転中など、画面を直接見ることが難しい状況でも、音声で情報を聞くことで「ながら作業」が可能です。
ウェブサイトの情報をより多くの場面で活用できるようになるため、ユーザーの利便性が飛躍的に向上します。
企業側の2つのメリット
音声読み上げ機能の導入は、企業にも「顧客層の拡大と企業イメージの向上」と「SEOへの好影響」という、2つのメリットをもたらします。
まず、「顧客層の拡大と企業イメージの向上」についてです。
音声による情報提供が可能になることで、これまでウェブサイトにアクセスできなかった視覚障がいのある方や高齢者など、新たなユーザー層を獲得できます。
日本社会は高齢化が進んでおり、この層をターゲットにすることは、ビジネス拡大にもつながるでしょう。
また、アクセシビリティに配慮した企業として、社会貢献活動(CSR)への取り組みを対外的にアピールできます。
企業の信頼性を高め、社会からの評価を向上させる上でも効果的です。
次に、「SEOへの好影響」についてです。
音声読み上げツールがスムーズに読み上げられるようにするには、ウェブサイトの構造を論理的かつ適切にマークアップする必要があります。
そうすることで、Googleなどの検索エンジンのクローラー(ウェブサイトを巡回して情報を収集するプログラム)にとっても、ウェブサイトが理解しやすいものとなります。
見出し・段落・代替テキストなどが正しく設定されていると、検索エンジンがコンテンツの内容を正確に把握しやすくなり、結果として検索順位の向上につながる可能性があります。
つまり、音声読み上げへの対応は、ウェブサイトのSEO対策にもなるのです。
音声読み上げ機能導入時の注意点|効果を最大化するために
「音声読み上げ機能があれば、アクセシビリティは完璧だろう」と考えてしまいがちですが、実はそうではありません。
ここでは、音声読み上げ機能を最大限に活用するために、ウェブ担当者が知っておくべき注意点を3つ解説します。
ウェブサイト自体のアクセシビリティが不可欠
音声読み上げ機能はウェブサイトの情報を音声に変換する役割を果たしますが、その「元となる情報」が適切に整理されていなければ、正しい音声を届けられません。
ばらばらのメモをそのまま読み上げても、内容が頭に入ってこないのと同じです。
ウェブサイトのコンテンツがHTMLタグで適切に構造化されていることが重要です。
例えば、ページの見出しが<h1>や<h2>といった正しいタグで構成されていない場合、音声読み上げ機能はそれをただの文字の羅列として認識し、情報の階層を伝えられません。
また、商品画像などに代替テキスト(alt属性)が設定されていなければ、音声では単に「画像」としか読み上げられず、肝心の内容が伝わらないままになってしまいます。
こうした基本的な対応は、音声読み上げを機能させるための土台となるのです。
複雑な構成では機能が不十分に
ウェブサイトの構造が複雑すぎると、音声読み上げ機能がうまく働かないことがあります。
複数のカラムに分かれたレイアウトや、JavaScriptに大きく依存した操作性を持つサイトは、読み上げの順番が不自然になったり、ユーザーが操作しようとしても反応がなかったりする原因になります。
例えば、キーボードで操作すると、メニューやボタンを飛ばして予期せぬ場所にフォーカスが移動してしまうようなケースです。
これでは、ユーザーは途中で操作を諦めてしまいます。
音声読み上げ機能の導入を検討する際には、こうした裏側のコーディングや構造が誰にとっても分かりやすく、論理的な順序になっているかを事前に確認することが大切です。
専門ツールによる網羅的な対応
ウェブサイトのアクセシビリティに配慮したコーディングや構造を、すべてのページで手作業でチェックし、修正していくのは現実的に困難です。
特に、更新頻度が高いサイトやページ数が多いサイトでは、手作業での対応はほぼ不可能と言えるでしょう。
効率的かつ確実にアクセシビリティの問題を洗い出し、改善するためには、専門のアクセシビリティツールを活用するのが賢明です。
例えば「Accessdove」は、ウェブサイト全体を自動的にスキャンし、人間では見落としがちな問題点まで網羅的に検出してくれます。
ウェブ担当者の負担を大幅に減らしながら、音声読み上げ機能の効果を最大限に引き出すための、根本的な改善を実現できるのです。
まとめ|音声読み上げ機能は「アクセシビリティ対応」とセットで
音声読み上げ機能は、ウェブサイトの情報を音声で聞けるようにすることで、目の不自由な方や高齢者だけでなく、すべてのユーザーの利便性を高める機能です。
企業の社会的責任を果たすだけでなく、新たな顧客層の獲得やSEO効果など、ビジネス的なメリットももたらします。
しかし、ただ機能を導入するだけでは不十分で、ウェブサイト自体のアクセシビリティを確保することが重要です。
音声読み上げ機能の効果を最大限に引き出すためにも、「Accessdove」などの専門ツールを活用し、網羅的なウェブアクセシビリティ対応を進めましょう。


