- ウェブサイトの「文字サイズ変更機能」はなぜ必要?アクセシビリティ対応のポイントとメリットを解説!
- ウェブサイトの「音声読み上げ機能」とは?利用者から見たメリットと導入時の注意点を解説!
- 情報バリアフリーとは?ウェブサイトにおける重要性と実現のためのポイントを解説!
- 2024年4月施行「障害者差別解消法」改正とウェブ対応の義務化|企業が今すべきこととは?
- ウェブアクセシビリティ対応はなぜ必要?導入のメリットから義務化の動向まで徹底解説!
- ウェブアクセシビリティとは何か?初心者向けにわかりやすく解説
- ウェブアクセシビリティの義務化はいつから?罰則はあるの?
- ウェブアクセシビリティのJIS規格について徹底解説!
- ウェブアクセシビリティの「A」「AA」達成基準を詳しく解説!
- ウェブアクセシビリティのデメリット4つとその解決策
目次
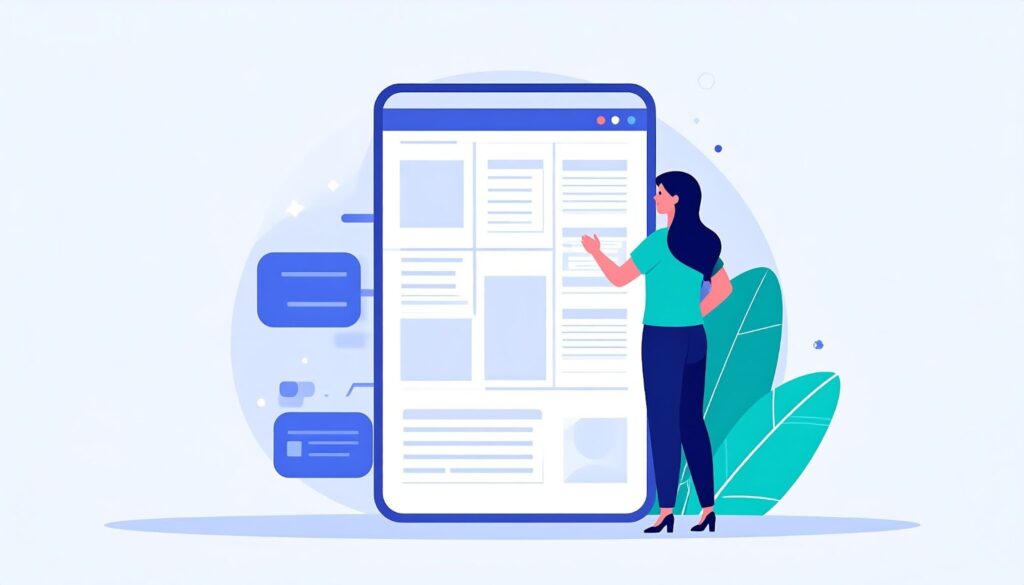
ウェブサイトを訪れる方の中には、「文字が小さくて読みにくい」と感じる方が少なくありません。
スマートフォンやパソコンの普及によって、誰もが情報にアクセスできるようになった今だからこそ、そうした方々にも快適に利用してもらうための配慮が必要です。
この配慮を「アクセシビリティ」と呼びます。
アクセシビリティとは、年齢や身体能力、利用環境に関わらず、誰もがウェブサイトやサービスを問題なく利用できるようにすることです。
文字サイズ変更機能は、読む人の見やすさに合わせて文字の大きさを自由に調整できる、利用者にとって便利な機能です。
「親切な機能」であるだけでなく、企業が提供する情報やサービスを、より多くの人に届ける役割も果たします。
この記事では、文字サイズ変更機能の必要性から導入することで得られるメリット、そして実装する際の注意点について解説します。
なぜ「文字サイズ変更機能」が必要なのか?
「文字サイズ変更機能」は多くのウェブサイトで導入されていますが、「なぜ今注目されているのか?」と感じる方もいるかもしれません。
ブラウザには標準で文字を拡大する機能もあるのに、わざわざサイト側にボタンを設ける意味は何でしょうか。
ここでは、Vサイトの「文字サイズ変更機能」が、現代においてなぜ重要なのかを解説します。
さまざまなユーザーのニーズに対応
ウェブサイトの文字サイズ変更機能は、さまざまなユーザーのニーズに応える施策のひとつです。
例えば、加齢とともに小さな文字をはっきりと読むことが難しくなる方は少なくありません。
老眼で遠近のピント調整がしづらくなったり、白内障などで視界がかすんだりすることも原因の一つです。
文字サイズ変更機能があれば、眼鏡や拡大鏡を使わなくても自分の見やすいサイズに調整できるため、ウェブサイトを快適に利用できます。
弱視の方にとっても、文字を大きくすることで初めて内容が認識できるようになる方もいます。
また、一時的な状況でも文字サイズ変更機能が役立つでしょう。
スマートフォンを屋外で使う際、強い太陽光の反射で画面が見えにくくなることがあります。
体調がすぐれず集中力が続かないときなど、誰もが文字が読みづらいと感じる状況は少なくありません。
こうした多様な利用環境に対応するためにも、文字サイズ変更機能が必要とされています。
ブラウザの機能だけでは不十分なケースも
「ブラウザのズーム機能を使えば文字を大きくできるのでは?」と思うかもしれません。
確かに、多くのブラウザには、画面全体を拡大する機能が標準で備わっています。
しかし、この方法にはいくつかの問題点があります。
最も大きな問題は、「レイアウトの崩れ」です。
ブラウザのズーム機能は、画面を一つの画像のように拡大するため、ウェブサイト全体のデザインや配置がずれてしまい、かえって見づらくなるケースが少なくありません。
文章が画面からはみ出したり、ボタンが押しにくくなったりすることで、ユーザーはサイトの利用を途中で諦めてしまう可能性があります。
一方、ウェブサイト独自の文字サイズ変更機能は、文字だけを拡大し、デザインの崩れを最小限に抑えられます。
見やすさを保ちながら、ユーザーを必要な情報に集中させることが可能です。
ブラウザ機能だけに頼るのではなく、サイト側で文字サイズ変更に対応することは、ユーザーの利便性を高める上で重要なポイントとなります。
「文字サイズ変更機能」がもたらすメリット(利用者側・企業側)
「文字サイズ変更機能」を導入することで、ウェブサイトを利用するユーザーはもちろん、サイトを運営する企業にとっても大きなメリットをもたらします。
ここでは、その具体的なメリットを、利用者側と企業側の両面から見ていきましょう。
利用者側のメリット
文字サイズ変更機能は、何よりもまずユーザー自身の体験を向上させます。
第一に挙げられるのが、「読者の負担を軽減する」ことです。
小さな文字を無理に読み続けようとすると、目の疲れ・肩こり・頭痛といった体の不調につながることがあります。
特に、ウェブサイトを長時間利用する際には、こうした疲労が読者のストレスとなり、離脱の原因にもなりかねません。
文字サイズ変更機能があれば、ユーザーは自分の視力や体調、利用しているデバイスに合わせて、文字を無理なく読めるサイズに調整できます。
また、「ユーザー体験(UX)の向上」にも大きく貢献します。
現代のウェブサイトは、パソコン・スマートフォン・タブレットなど、さまざまな画面サイズで利用されます。
ユーザーが自身の環境に合わせて文字を自由に調整できることは、ウェブサイトへの満足度を飛躍的に高めます。
自分が快適に使えるサイトだと感じれば、ユーザーは自然とリピーターとなり、ブランドへの愛着も深まっていくでしょう。
企業側のメリット
文字サイズ変更機能の導入は、企業にもメリットをもたらします。
まず、「顧客層の拡大」です。
文字が読みにくいという理由で今まで自社サイトを諦めていた高齢者や弱視の方々が、新しい顧客としてサイトを訪れてくれるようになります。
日本の人口に占める高齢者の割合は年々増加しており、この層にアプローチできることは、ビジネスチャンスを大きく広げることにつながります。
また、「法的要件への対応」という重要な側面もあります。
2024年4月に施行された改正「障害者差別解消法」では、民間事業者にも「合理的配慮の提供」が義務付けられました。
また、国際的なアクセシビリティガイドラインである「WCAG(Web Content Accessibility Guidelines)」も、ユーザーが文字サイズを200%まで拡大してもレイアウトが崩れないように求めています。
こうした基準に準拠することは、法律を遵守し、企業が社会的な責任を果たす上でも欠かせません。
アクセシビリティに配慮したサイトは、企業価値の向上にもつながり、投資家や社会全体からの評価を高める効果も期待できます。
関連記事:WCAG(ウェブアクセシビリティガイドライン)とは?今さら聞けない基本から対応のポイントまでを解説!
「文字サイズ変更機能」を実装する際の注意点
ウェブサイトに「文字サイズ変更機能」を実装する際、ただボタンを設置するだけでは不十分な場合があります。
ここでは、機能を効果的に活用するために、実装時に注意すべきポイントを見ていきましょう。
文字サイズ変更によるレイアウト崩れを防ぐ
文字サイズを大きくすると、当然ながらテキストが占める面積も増えます。
この変化にウェブサイトのデザインが対応できていないと、テキストが他の画像やボタンに重なって読みにくくなったり、画面の端からはみ出してしまったりする「レイアウト崩れ」が起こります。
そのような問題を避けるためには、ウェブサイト全体が文字サイズの変更に合わせて各要素の位置や大きさを自動的に調整するような設計になっていなければなりません。
具体的には、文字サイズを「px(ピクセル)」のような固定値で指定するのではなく、「rem」や「em」といった相対単位で設定することが推奨されます。
これらの単位は基準となる文字サイズに合わせて拡大・縮小するため、文字を大きくしてもレイアウトが崩れにくいというメリットがあります。
すべてのコンテンツが拡大可能かを確認
文字サイズ変更機能は、メインの文章だけが拡大されても意味がありません。
ユーザーが本当に知りたいのは、見出し・ナビゲーションメニュー・ボタンに書かれた文字など、サイトを理解し、操作するためのすべての情報です。
そのため、文字サイズ変更機能を実装する際には、サイト上のすべての文字が正しく拡大・縮小されるかを細部まで確認する必要があります。
特に、画像に埋め込まれた文字やJavaScriptで動的に表示される文字、フォームの入力欄などに使われている文字は、拡大に対応していないケースが少なくありません。
導入前に各要素が適切にコーディングされているかをチェックし、拡大に対応していなければ修正しましょう。
確認を怠ると、ユーザーはサイトの一部しか利用できず、結果的にウェブサイトのバリアフリー化が不完全なものになってしまいます。
効率的なアクセシビリティ対応は専門ツールで
文字サイズ変更機能の導入に伴う注意点をクリアするためには、ウェブサイト全体を網羅的にチェックし、専門的な知識に基づいて修正を施す必要があります。
ここでは、この手間と時間をいかに効率化できるかについて考えてみましょう。
手動チェックには限界がある
ウェブサイトのアクセシビリティ対応は、多くの項目にわたります。
文字サイズの調整・画像への代替テキスト設定・適切な見出し構造の整備など、すべてを手作業で確認するのは手間と時間がかかります。
特に、コンテンツの更新頻度が高いサイトやページ数が多いサイトでは、手動でのチェックは現実的ではありません。
また、手動でのチェックには、どうしても見落としが発生しやすいという限界があります。
例えば、HTMLのちょっとした記述ミスや、デザイン上では気づきにくいコントラスト比の問題など、専門的な知識がなければ発見しにくい問題も存在するのです。
手作業だけに頼ることは、対応の品質を担保しきれないリスクを伴います。
専門ツールを活用した網羅的な改善が効果的
文字サイズ変更機能を含め、網羅的なウェブアクセシビリティ対応を効率的に進めるには、専門のアクセシビリティツールを活用するのが最も効果的です。
こうしたツールは、ウェブサイト全体を自動でスキャンし、WCAG(ウェブアクセシビリティガイドライン)の基準に基づいて問題点を洗い出してくれます。
「Accessdove」では、文字サイズの不備だけでなく、画像への代替テキストや適切な見出し構造の有無など、多岐にわたる項目を自動でチェックします。
専門知識がなくても、タグ1行を埋め込むだけで問題を効率的に発見し、改善に向けた具体的な指針を得られます。
ウェブ担当者の負担を大幅に軽減しながら、サイト全体のアクセシビリティを継続的に向上させることが可能です。
まとめ
ウェブサイトに文字サイズ変更機能を設けることは、誰もが快適に使えるサイトにするための大切な取り組みです。
こうした対応は、企業の信頼を高め、新しい顧客層の獲得にもつながります。
文字サイズの問題に限らず、ウェブサイト全体のアクセシビリティを効率的に改善するには、「Accessdove」のような専門ツールの活用が有効です。
アクセシビリティ対応についてご不明な点がある場合や、文字サイズ変更機能を手軽に実装したい方は、30日間の無料トライアルもございますので、「Accessdove」までお気軽にお問い合わせください。


