ウェブアクセシビリティの義務化はいつから?罰則はあるの?
目次

2024年4月に障害者差別解消法が改正され、合理的配慮の提供が義務化されました。合理的配慮とは、障がい者が社会参加する際に対面する障壁を取り除くために必要な調整や適応を行うことを指し、ウェブアクセシビリティの確保もその一環です。
本記事では、ウェブアクセシビリティと義務化の概要や訴訟事例、対応方法について詳しく解説します。ウェブアクセシビリティの義務化や対応しない場合のリスクについて知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
ウェブアクセシビリティとは?

ウェブアクセシビリティとは、年齢や障害の有無に関わらず、すべての人がウェブサイトやオンラインサービスを支障なく利用できるようにすることです。ウェブアクセシビリティの具体例は以下の通りです。
- 映像に字幕や手話通訳をつける
- わかりやすい色彩やフォントサイズにする
- 画像には代替テキストをつける
- キーボードだけで操作可能にする
- 指示とエラーメッセージでわかりやすくする
ウェブアクセシビリティの詳細については、以下をご覧ください。
⇒ウェブアクセシビリティとは何か?初心者向けにわかりやすく解説
ウェブアクセシビリティ対応は義務?詳しい概要

障がい者差別解消法の改正により、2024年4月1日から全ての民間企業でも障害者に対する合理的配慮が義務化されました。合理的配慮とは、障がい者や高齢者などの障壁を取り除くための対応で、かつ事業者の負担になり過ぎないもののことです。
合理的配慮の提供が義務化されていますが、ウェブアクセシビリティ自体は合理的配慮を行う上での環境整備の1つとして努力義務となっております。どこまでの対応が求められるかは、事業者の状況により異なります。ここからは、以下について詳しく解説します。
- 義務化の背景
- 適用事業者の範囲
- 実施基準とガイドライン・規格
- 対応しない場合の罰則
義務化の背景
障害者への合理的配慮が義務化された背景には、大きく分けて4つの理由があります。
- 国際的な動向: 障害者の権利に関する国際的な基準が高まっていることが大きな要因です。特に、2006年に国連が採択した「障害者権利条約」では、障害者の社会参加を確保するために合理的配慮の提供が求められています。日本はこの条約を批准しており、それに基づいた国内法整備が必要とされています。
- 多様性とインクルージョンの重視: 社会全体で多様性と包摂(インクルージョン)を重視する考えが進展してきたことも背景の一つです。障害を持つ人々も、健常者と同様に社会で活躍し、自己実現できる環境を整えることが求められています。
- 実効的な権利保障の必要性: 障害者が実際に差別から守られ、公平に社会参加できるようにするためには、法律による義務化は非常に効果的です。義務化することで、すべての事業者が一定の基準を満たすよう努めることが期待されます。
- 障害者からの声: 障害を持つ方々からの「もっと社会参加を進めてほしい」「不便を感じている」という声を反映する形で、法律の改正が進められました。
適用事業者の範囲
これまでは、障害者への合理的配慮は国や地方公共団体などの公的機関のみに義務化されていました。しかし、法律の改正により2024年4月1日以降、全ての民間企業においても合理的配慮が義務化の対象となっています。
実施基準とガイドライン・規格
ウェブアクセシビリティの確保に向け何をするべきか、各事業者が独自に障がい者や高齢者などのニーズを調査・把握することは困難です。ガイドラインと規格が設けられているため、ウェブアクセシビリティ対応する際に活用しましょう。ここからは、主な規格であるWCAGとJIS X 8341-3について詳しく解説します。
WCAG(W3Cの規格)
WCAG(Web Content Accessibility Guidelines)は、W3C(World Wide Web Consortium)が定めた国際的な基準です。
ウェブサイトを作る人たちが、誰でも使いやすいサイトを作るために守るべきルールや基準のことです。簡単に言うと、どんな人でもインターネットを快適に使えるようにするためのガイドラインです。日本で適用されているJIS規格のもととなっているものです。1999年に初めてウェブアクセシビリティ対応に向けたガイドラインが作成され、2023年10月5日には最新版のWCAG 2.2が策定されました。
JIS X 8341-3(日本国内規格)
JIS X 8341-3は、WCAGをベースに制定された日本国内の規格です。そもそも、JIS(Japanese Industrial Standards、日本工業規格)とは、日本国内における工業標準化の促進に向け、日本工業標準調査会(JISC)が制定している規格のことです。JIS X 8341において、情報通信における機器やソフトウェア、サービスのアクセシビリティ確保・向上に向け、配慮すべき具体的な要件がまとめられています。政府や大企業の多くが、JIS X 8341-3をベースにしており、国内のみで活動する場合はJIS X 8341-3に準拠すれば問題ありません。
なお、規格の詳細は以下をご覧ください。
⇒ウェブアクセシビリティのJIS規格について徹底解説!
対応しない場合の罰則
現時点では、ウェブアクセシビリティに未対応であった場合の罰則は設けられていません。ただし、行政機関などから合理的配慮の未提供に関する指摘があった場合、報告義務があります。万が一、虚偽の報告や報告をしなければ、20万円以下の罰則が科せられるケースがあるため、注意が必要です。
ウェブアクセシビリティに未対応の場合における訴訟リスクと事例

ウェブアクセシビリティへの注目は世界中で高まっており、義務化している国も多く存在します。ここからは、 ウェブアクセシビリティに未対応の場合における海外の訴訟リスクと以下の事例について詳しく解説します。
- シドニーオリンピック
- ドミノピザ
- 日本の人気アパレルブランド
海外におけるウェブアクセシビリティ対応
日本のみならず、世界における多くの国々では法律やルールを整備し、ウェブアクセシビリティ対応の義務化を進めています。具体的な国・地域と法律の一部の例は以下の通りです。
- アメリカ:リハビリテーション法508条(Section 508 of the Rehabilitation Act)、アメリカ障害者法(Americans with Disabilities Act)
- 欧州連合(EU):ウェブアクセシビリティ指令(Web Accessibility Directive)、欧州アクセシビリティ法(European Accessibility Act)
- ニュージーランド:Web Accessibility Standard1.0
- オーストラリア:1992年障がい者差別禁止法(Disability Discrimination Act 1992)
- 韓国:障害者差別禁止および権利救済に関する法律(장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률)情報通信振興法(정보통신촉진법)
- カナダ:カナダ・アクセシビリティ法(Accessible Canada Act (ACA))
法規制が進むとともに、訴訟事例も増加しています。アメリカでは、2015年に100件未満だったウェブアクセシビリティ関連の訴訟が、2022年には3,000件程度になったと言われています。UsableNetの報告によれば、2023年の訴訟件数は4,605件です。
参照:2023年デジタルアクセシビリティ訴訟に関する中間報告書|UsableNet
ドミノピザの訴訟事例
2016年には、ドミノピザがアメリカの視覚障がい者に訴えられました。原因は、Webサイトとアプリがウェブアクセシビリティに対応しておらず、注文やクーポン利用ができなかったことです。2021年に連邦地裁が視覚障がい者の勝訴判決を下し、ウェブアクセシビリティへの対応と、4,000ドルの損害賠償支払いをドミノピザに命じました。
シドニーオリンピックの訴訟事例
2000年に開催されたシドニーオリンピックで、ウェブアクセシビリティに関する訴訟が起こりました。日常的に点字ディスプレイを使用している視覚障がい者が、オリンピックの公式Webサイトがウェブアクセシビリティ対応しておらず、情報格差が生まれていることが差別であると訴えました。その結果、HREOCは被告に対して2万オーストラリアドル(約200万円)の損害賠償支払いを命じました。
参照:アクセス不能の教訓:シドニーオリンピックのウェブサイト|W3C
日本の人気アパレルブランドの訴訟事例
2017年には日本の大手アパレルブランドのECサイトが、アクセシビリティに未対応だったため、アメリカで訴訟されました。視覚障がい者の方が、以下の原因で商品購入ができず、法律違反を主張しました。
- 画像などに代替テキスト(alt)が提供されていなかった
- リンクに遷移先を示すラベル情報がなかった
訴訟に関するサイト⇨https://www.classaction.org/media/jorge-v-uniqlo-usa-llc.pdf
このように、インターネットのアクセシビリティは近年ますます重要視されており、日本企業も例外ではありません。先進国、特にアメリカなどでは、法律に基づいてウェブサイトのアクセシビリティが厳しく要求されています。これを満たさない場合には、高額な賠償金を伴う訴訟のリスクがあります。
日本も海外に倣ってアクセシビリティ対応の強化が進むと考えられており、今のうちに対応することが企業にとって重要です。積極的な取り組みが、リスクを回避するだけでなく、将来的な競争力を高める鍵となります。
ウェブアクセシビリティへの対応方法
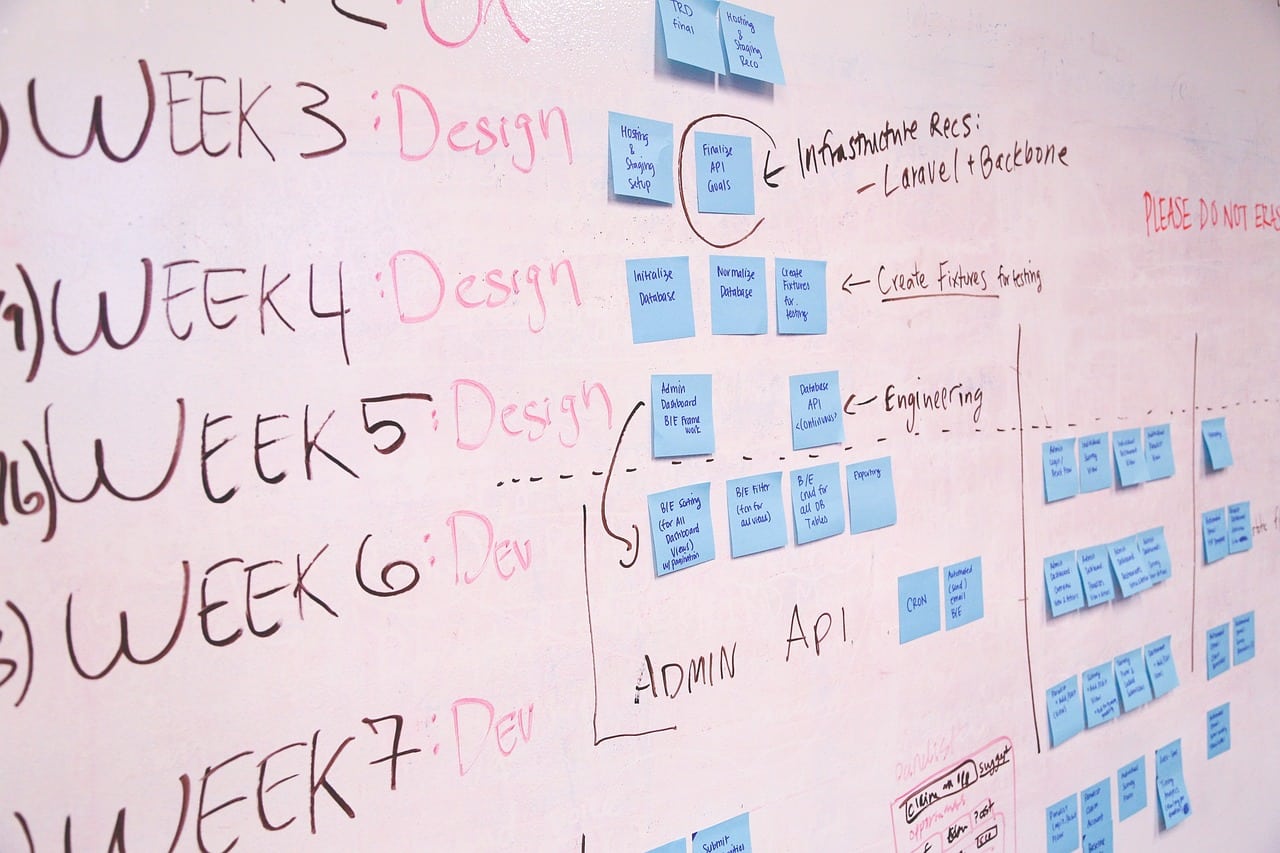
ウェブアクセシビリティへの対応は、以下のステップで行うと良いでしょう。
- 対応規格の検討・決定
- 適合レベルと対応度の検討・決定
- ウェブアクセシビリティ方針の策定
- コンテンツの作成とウェブアクセシビリティ試験の実施
- 試験結果の公開
- 継続的な運用体制の構築
対応は一度行えば完了するものではありません。法規制やニーズなども変化するため、定期的な確認と改修が必要です。
なお、ウェブアクセシビリティ対応の詳細については、以下をご覧ください。
⇒webサイトをアクセシビリティ対応は何をすれば良いの?具体的な流れを解説!
まとめ

障がい者差別解消法の改正により、2024年4月1日から全ての民間企業でも障害者に対する合理的配慮の提供が義務化されています。現時点では、ウェブアクセシビリティへの対応が義務化したわけではありませんが、事業者の負担にならない範囲でのアクセシビリティ対応は必要です。
アクセシビリティ対応に向けたWebサイトの改修には、手間やコストがかかります。対応する際は、ツールも上手に活用しながら無理のない範囲での実施をすると良いでしょう。


